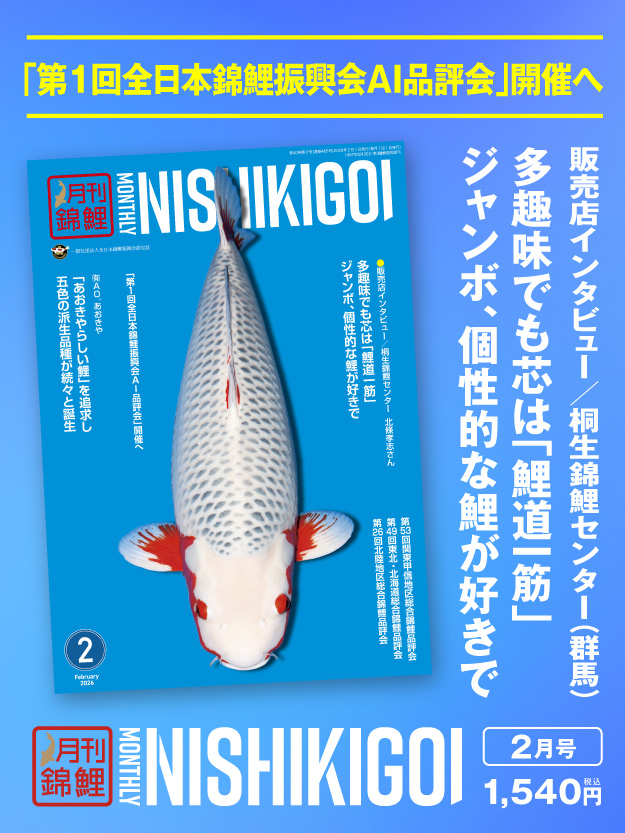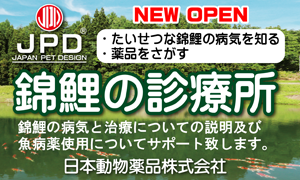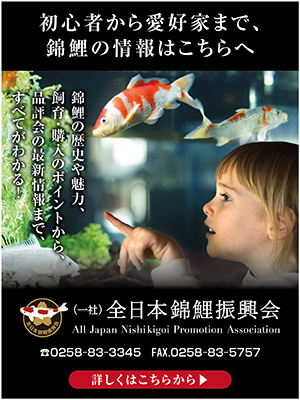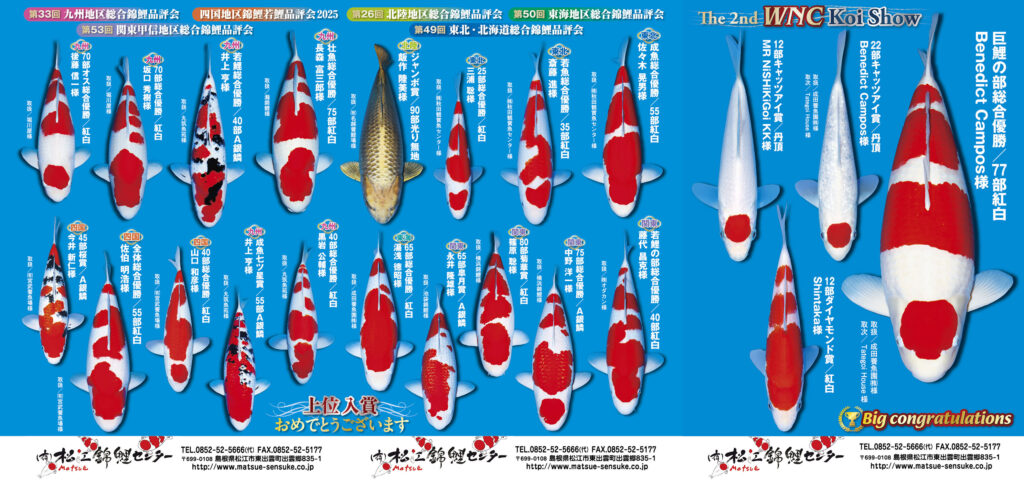稚魚池は面数より回転重視へ
病気に苦悩も周りのサポートで
―以前の取材時には御三家と白写り、秋翠、孔雀を作っているとおっしゃっていましたが、現在のラインナップは?
玉浦 今年は三色が9腹、紅白が3腹、昭和が3腹で孔雀が1腹です。当時三色は3腹だったので、腹数で言えばかなり増えましたかね。
―それはやはり試し腹をいくつか採りたいからですか。
玉浦 試しと保険で。なのでいっぱい飼うのはこれとこれとこれ、みたいな感じであとはちょっとずつと。
うちの場合はワンシーズンで三毛作目までやるんですけど、そうするとよそに比べて飼育期間はすごく短くなります。模様がはっきりしているわけではないから、本当によくわからないのがいっぱいいて、選別してても「よくわからんのう」と。特に一毛作目の三色なんかはわかりずらくて。
―今は野池に稚魚を放してから、だいたい45日ぐらいまで待って選別をする人が増えてきていますよね。
國則 業界的にはそこの時間はわりと長くしようというのが主流になっていますね。それにそのほうが鯉が強くなるとも。だけどうちは極力たくさん採って、次を早くという考えがいいと思ってやっています。
―なるほど。やり方はそれぞれの養鯉場で異なりますからね。
玉浦 うちはだいたいゴールデンウィーク明けから一毛作目を始めて、6月の半ばぐらいに一次選別があるので、そのタイミングで二毛作目を採って、選別で空いた池に毛仔を入れられるようにやっています。


―選別をしながら池が空かないように、タイミングよく採っていくわけですね。
玉浦 産卵がずれると、池が空いたままで何日もおいておかなければいけないので、もったいないじゃないですか。うちの場合は二毛作目からが勝負みたいな。梅雨があるけど気候が安定していますので。
―気温が安定することで稚魚の育ちがよくなると。
玉浦 やろうと思えば四毛作までできます。5月の初めに一毛作目をセットして、8月の第一週までは稚魚を放すことができるので。気温が高くなれば、だんだんと選別のタイミングが早くなっていくので、池に入れて20日ぐらいで選別ができてしまうから、網を引いたらすぐに毛仔を入れられるように準備を。
―かなりタイトなスケジュールですよね。
玉浦 ですので、この日に孵化するというのが絶対条件だから、自分が使いたい親というよりかは、絶対に産む親を優先して。
―自分がすごく採ってみたい鯉だとしても、そういった産まないリスクが少しでもあると、スケジュールが崩れてしまうわけですか。
玉浦 そうそう。一番はやはりスケジュールを優先。だけどそれだとあまり良いのが残らないような気もしているので、今は三毛作でも全部が全部ではなく、そんなに無理をせずに部分的にやるようにしています。
―暑い時期の産卵はうまくいくものですか?
玉浦 だいたい三毛作目を採るのが7月の後半ぐらいだから、暑くなり始めてはいるけどなんとかまだ親がいけるかなという感じで。
國則 ギリギリですね。もう1週間あとだったらちょっときびしいかなと。生んだとしてもちょっと。
玉浦 生むことは生むんだけど受精率が悪くて孵化しなかったり、孵化しても死んでしまったりとかはあります。
―三毛作を行うのは稚魚池が限られているからですか。今後増やしていこうというのは?
玉浦 稚魚の分母が多ければ多いほど、良い鯉ができやすいというのが一般的な考えじゃないですか。だから他の生産者は池を増やしていると思うんだけど、それは完全に手があった場合ですよね。面倒を見られないのに池に投げていても絶対できないから、うちは稚魚池の面数を減らして、少ない池を回転させるようにしています。
―稚魚池の面数で稚魚の数を稼ぐのではなく、効率よく回転させることで限られた人手の中で数を稼いでいくわけですか。
玉浦 そうですね。ピーク時には50面ぐらいありましたけど、今は34面まで減らしました。野池といってもいろいろなものがありますから、手間ばっかりかかってあんまりあがりが悪いような池を、どんどん減らしていっているわけです。
―ピーク時と比べるとだいぶ減らしましたね。
玉浦 その頃はミジンコがいようがいまいと、毛仔を入れればできるという感覚でしたので(笑)。今はそうではなくて、できる限り努力してミジンコを湧かせて。使いやすい野池だけで回転させていったほうが、良いという考えでやっています。
國則 うちはどちらかと言えば分母を減らしながらも、いかに分子を増やして効率をあげられないかという話はずっとしています。