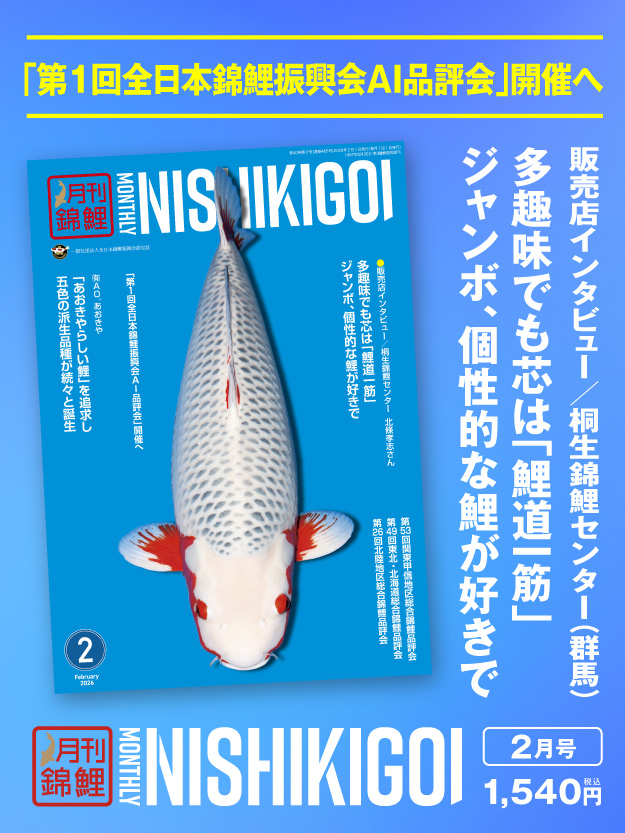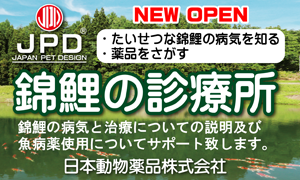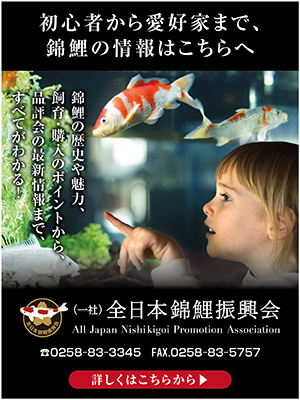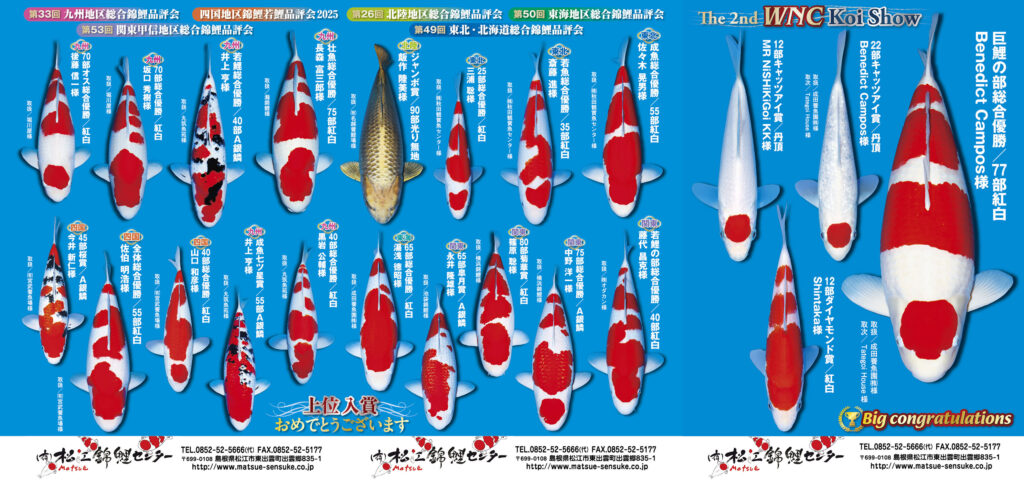取材時の7月下旬に与えていた餌は、愛好家では比較的珍しい浮きと沈みのミックスで、高水温用の沈下に、パラクリアとメディKの浮上を使用。こだわりがうかがえる餌の選択は、「メディKは鯉の健康のために良い餌ということですし、パラクリアはエラを守ってくれるということで使っています。沈みは初めて使ったんですが、8月〜9月で使い切ると思うので、そこで体の張りなどを見て、その後も使い続けるかどうか判断したいと思います。餌はこの1か月半でトータルで24㎏くらい使いましたから、うちの鯉の数からするとかなり多いほうではないでしょうか」
川上さんの飼育では量を与えることが基本になるため、水の状態には当然気を使う。それぞれのFRP水槽にもともと備えつけられている濾過槽は、現在は沈殿槽のような役割を担っており、5日に1回は掃除している。当歳用コンテナの濾過槽はさらに頻度が高く、3日に1回の洗浄が必須だという。
「そのぐらいの間隔でやらないと臭くなってくるんです。特に当歳は、冬は24℃にして餌をバンバンやりますから。だから5日、3日と決めてカレンダーに印を付けておくんですよ。面倒だなと思うときもありますけど、それだけは必ず……仕事より真面目にやってますよ(笑)。そうやって当歳のときさえ気をつければ、2歳、3歳になって死ぬことはまずないですね」
4歳以上のFRPは、60㎝〜70㎝後半という鯉のサイズや給餌量を踏まえて湧清水10型を使用。1・8トンの水量に対してかなり余裕をもたせていて、400リットル濾過槽との組み合わせで水は良い状態をキープしている。多いときは同サイズの鯉がさらに2〜3本増えるというこの環境で、どの鯉も大きく健康に育っているのは、食い込ませるために水質の悪化を防ぐことがいかに大切かを物語っているようだ。
「これだけ餌をやっても水が汚れないというのは、やはり湧清水の力が大きいんでしょうね。あれがないと食いが止まるような気がします」
川上さんが購入するのは基本的に当歳で、まずはそれらをコンテナで加温越冬飼育。その後オスは2〜3歳用のFRPに移し、7月下旬で最大50㎝に達するという。そして2年間の飼育で特に綺麗になったものを、4歳以降用のFRPに移動するという流れだ。
「例えば3月号の表紙に掲載したオスの昭和(第51回関東60部総合)は、当歳で買ってずっとうちの池で飼育して、野池には一度も入れていませんけど、3歳(受賞時)でここまで大きくなるんですよ。今はオスでも綺麗だし、メスと変わらない良い鯉がいますから。それに、メスに同じように餌をやったら腹に来るんじゃないかな。それはいつか試してみようと思っています」


自宅飼育での受賞が自信に
SNSで発信、「この設備でも」
川上さんが本格的に錦鯉の飼育を始めたのは「1坪池バンザイ」の5年ほど前から。当時はオスへのこだわりはなく、「メスのほうが太くなるから良いというようなレベルでした」と話す。
ただ、広島県の実家の庭池で父親が鯉を飼っていたことから、鯉は少年時代から身近な存在だった。父とともに竹田養鯉場(広島市)などを訪れ、鯉を選ばせてもらうこともあったという。
「僕自身が育てていたわけではなかったんですが、選ぶのは楽しかったです」という川上さん。社会人として収入を得るようになってからは、実家に帰ったときに竹田養鯉場などで購入してそのまま池に入れたりと、鯉との関わりが途切れたことはなかった。将来、自分でも鯉を飼いたいという気持ちは常に持ち続けていたといい、現在の自宅の完成に合わせてFRP水槽を注文していたほど。初期は、子供の頃からのなじみだった竹田養鯉場に鯉を送ってもらうことが多く、1坪池バンザイの写真に写っている大半が竹田産だ。