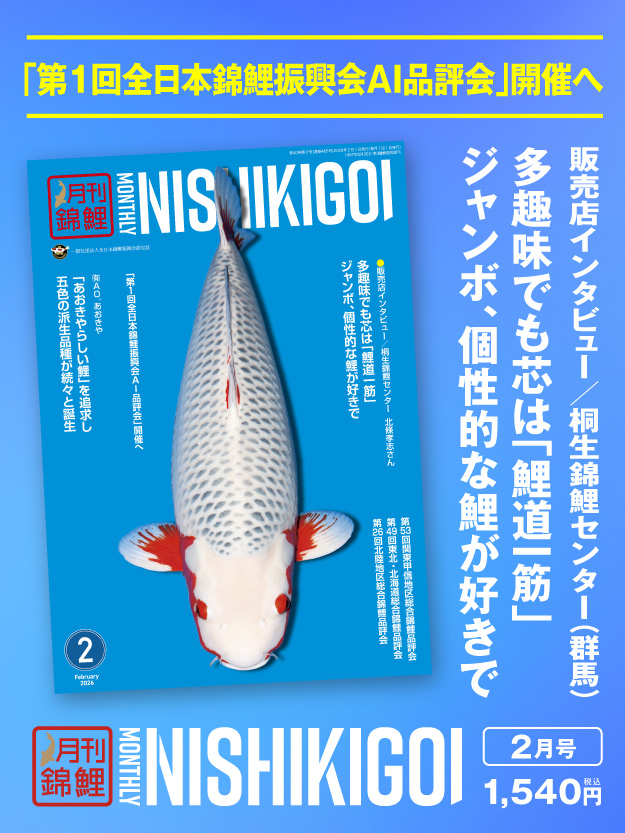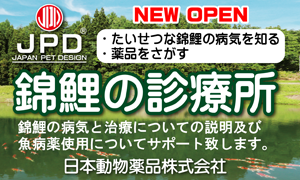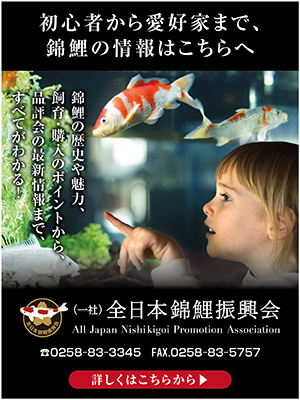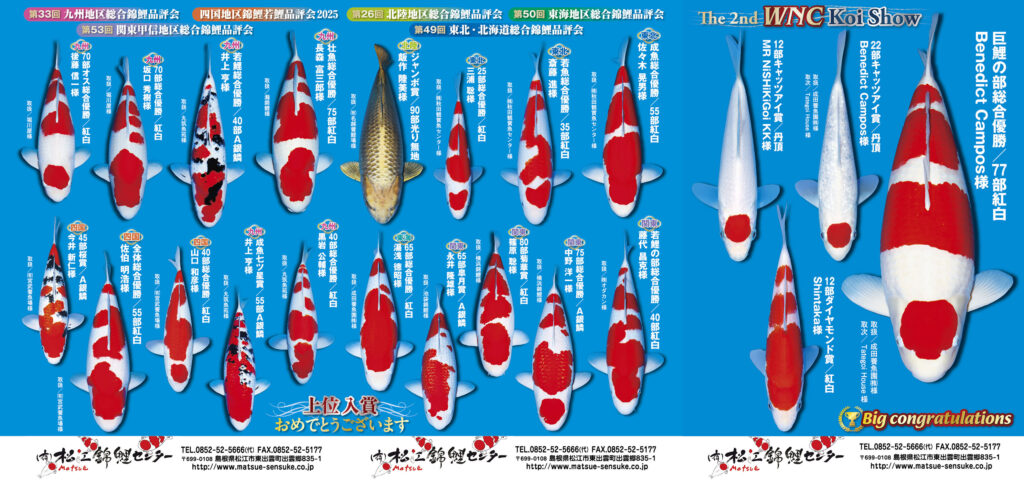「養鯉場を…」湧き上がる思い
YouTubeは伝えやすさが利点
猪狩さんの錦鯉飼育のスタートは今から約6年前。自宅を建てるのと同時に、庭に石組みの小さな池を作ったのが始まりだ。
「子供の頃から魚が好きで、熱帯魚などを飼っていたんです。その後、日本の魚、大きくて綺麗な魚ということで錦鯉にたどり着きました。それで池を作って、ネットで買った鯉を泳がせていました」
ただ、池が1m×1・5mほどと小さかったこと、循環はウォータークリーナーのみだったことから水作りがうまくいかず魚が見えないことに加え、子供の安全を考えて「これではダメだ」と埋め戻すことに。そして4トンのフレームプールで再スタートした。




趣味として鯉と接する日々が続く中、猪狩さんの心の奥から「養鯉場をやりたい」という気持ちが湧き上がってくる。昨年3月に藤田養魚を訪れ、思い描く将来像を相談した猪狩さん。藤田さんのアドバイスとバックアップによって、同場産の鯉の販売をヤフオクとホームページで開始。同年末に、現在のやり方であるYouTubeでの販売鯉紹介に切り替えた。その時点ですでにYouTubeを始めて1年半以上が経過しており、一定数のフォロワーがいたこともあり当初から売れ行きは好調だったという。
「今は一回の販売で3分の1が新規、3分の2がリピーターという内訳なんですが、今後はさらにリピーターさんを増やして基盤を固めつつ、新規のお客さんを開拓するためにもYouTubeをさらに伸ばしていく必要があると思っています」
ヤフオクやホームページでの販売よりYouTubeが優れている点について、「動画で鯉の動きに合わせて喋れるので、どんな鯉か伝えやすいんです。『体格が良い』『ここに良い墨があって』とか、それに共感してくれる人は買いやすいんじゃないでしょうか」
動画だけでなく、実物を見たいという人に対しては自宅への訪問も受け入れており、これはネットでの活動が中心の「錦鯉系YouTuber」としては珍しい。中には山形から訪れる人もいるという。

大きな可能性を秘める潜在層
まずはネット、将来は実店舗も
錦鯉業界の現状を説明するとき、「海外輸出は好調だが、日本国内は元気がない……」というのはもはや定型文だ。この根拠は、全日本などの国際品評会における日本人と外国人の出品数比率、入賞比率、ローカル品評会の出品数減少、愛好会の会員減少などがある。
ただ最近、この情報だけで日本人愛好家が減っていると判断するのは早計ではないかと思わせるのが、錦鯉関連のYouTube動画が軒並み数千、数万の再生回数を記録していること。錦鯉をまだ飼っていないが興味を持っている人たちや、飼っていても品評会に出品しない、愛好会にも所属していない愛好家は、実はかなり多いのではないか? という気もする。そのような層にとっての入口となるため、錦鯉の世界により深く引き込むために、錦鯉の楽しさ、素晴らしさを積極的にアピールしてくれる人の存在は、業界にプラスの作用をもたらすはずだ。ヤフオクなども含めたネット販売店は玉石混交だが、実店舗に敷居の高さを感じている人や、近隣に販売店がない人たちの受け皿になっているのは間違いない。
「先ほど話したように、関東圏のマンションに結構送ったりするので、水槽で飼っている人は多いような気がします。意外と『ここにもいた』『あそこにもいた』というように、錦鯉を飼っている人が発見されていく感じです。そういう人たちをどうやって次のステップ、品評会に連れていくかというのも課題でしょうね。品評会への参加を促す動画を作ろうかと藤田さんと話をしています」
今後、さらに本格的に事業を展開していくために、振興会への加入も考えているという猪狩さん。品評会での実績も必要になってくるだろう。
「仕入れは安定してできるようになったんですが、販売については売れる時期と売れない時期の波がどうしてもあります。まだ鯉一本ではやっていけなくて、今は勤めと二足のわらじですが、将来的には土地を買ってビニールハウスを増やして、現地で販売できるようになればいいなと思っています。そのためにもYouTubeをもっと充実させて、多くの人に錦鯉に興味を持ってもらえるようにしたいですね」